がんになりたくなければ、
ボケたくなければ、
毎日コーヒーを飲みなさい。
ボケたくなければ、
毎日コーヒーを飲みなさい。
岡 希太郎 (著)
コーヒーに含まれるカフェインとポリフェノールは日本茶よりも多く、その相乗効果がビジネスマンの健康を守る。コーヒーが生活習慣病予防に大いに役立つ飲み物であることをわかりやすく解説。
第1章 コーヒーは本当に体にいい
/ コーヒーの起源は「くすり」
コーヒーは肝炎ウイルスの増殖を抑える
コーヒーは動脈硬化に有効
糖尿病と脳卒中の予防にも朗報
コーヒーとさまざまながん予防の期待
2型糖尿病をコーヒーで予防
パーキンソン病予防の期待
百薬の王コーヒーがアルコールの毒を消す
他にもあるコーヒーの毒消し作用
紫外線による、シミ、皮膚がん予防
ぺアを組むと強く働く力フ工イン・パワー
がんの最先端治療に希望
ポリフ工ノールとは何か
ニコチン酸とNMP
コーヒーvsお茶
カフェインとポリフェノールの相乗効果
コーヒーと脳とアルツハイマー病の関係
コーヒーが認知症リスクを回避
アルツハイマー病を発症する前に
進むアルツハイマー病とコーヒーの研究
コーヒー飲んで脳トレーニング
コーヒーは貧血の特効薬になるか?
コーヒーは冷えるに根拠なし
コーヒーは特保を超えた
飲みすぎは逆効果
コーヒー・卜リビア
その1:最初のチップ
その2:法王から洗礼を受けたコーヒー
その3:ナポレオンとコーヒー
その4:日本初の喫茶店
第2章 どんなコーヒーをどのように飲むといいのか?
アラビ力種と口ブスタ種
浅煎り・深煎りで変わる成分
煎りの深さの違う豆で「成分ブレンド」
がんを予防するコーヒーは
糖尿病を予防するコーヒーは
アルツハイマー病を予防するには
悪玉成分を除く技術
カフェイン入りかデカフェタイプか?
がんを予防するコーヒーは
コーヒーの成分を生かすために覚えておくといいこと
その1:温度と蒸らし時間
その2:コーヒーの種類と作用の違い
〈インスタントコーヒー〉
〈缶コーヒー〉
その3:砂糖とミルク
その4:ダイエットなら食前に
その5:豆の挽き方
その6:コーヒー豆の保存と有効成分
その7:便利な滝れ方・飲み方
コーヒーをよい意味で「癖」にする
1日何杯まで飲んでいいか?
第3章 食と長寿と病気予防
必須栄養素とコーヒーの相乗効果
重要なのは約50種の必須栄養素
なぜ必須栄養素をとらねばならないのか
ポリフ工ノールは混ぜると効く
カロリー制限より必須栄養素
「肉より魚」ではなく「5品より10品」
味と色は栄養選びのめやす
栄養素を助けるコーヒー成分
カルシウムを減らさないコーヒーの飲み方
コーヒーは肝臓の寿命を延ばすか?
コーヒーは尿酸値のバランスをとるか?
コーヒーは「オートファジー」を助けるか?
コーヒーで腸内細菌が元気に
コーヒーは本当に体にいい
コーヒー活用アドバイス
◇35歳、スーパーマーケット店長の減量計画
◇35歳、霞が関キャリアの生活改善
病気の初期症状を見逃すな
ほか
岡 希太郎 (著)
新書判:160ページ(H)17.6cm x (W)11.4cm
出版社:集英社
岡希太郎[おか きたろう]
1941年東京都出身。東京薬科大学名誉教授、金沢大学コーヒー学講座講師。東京薬科大学卒業、薬学博士(東京大学)。スタンフォード大学医学部留学。薬化学と臨床薬理学を専攻。加盟学会:日本薬学会、米国化学会、日本臨床薬理学会、日本コーヒー文化学会他。著書に「臨床薬理学J(朝倉書庖)、「なるほどくすりの原料としくみ」(素朴社)、「コーヒーの処方箋」「珈琲一杯の薬理学」「医食同源のすすめ死ぬまで元気でいたいなら」(以上医薬経済社)等
コーヒーに含まれるカフェインとポリフェノールは日本茶よりも多く、その相乗効果がビジネスマンの健康を守る。コーヒーが生活習慣病予防に大いに役立つ飲み物であることをわかりやすく解説。
第1章 コーヒーは本当に体にいい
/ コーヒーの起源は「くすり」
コーヒーは肝炎ウイルスの増殖を抑える
コーヒーは動脈硬化に有効
糖尿病と脳卒中の予防にも朗報
コーヒーとさまざまながん予防の期待
2型糖尿病をコーヒーで予防
パーキンソン病予防の期待
百薬の王コーヒーがアルコールの毒を消す
他にもあるコーヒーの毒消し作用
紫外線による、シミ、皮膚がん予防
ぺアを組むと強く働く力フ工イン・パワー
がんの最先端治療に希望
ポリフ工ノールとは何か
ニコチン酸とNMP
コーヒーvsお茶
カフェインとポリフェノールの相乗効果
コーヒーと脳とアルツハイマー病の関係
コーヒーが認知症リスクを回避
アルツハイマー病を発症する前に
進むアルツハイマー病とコーヒーの研究
コーヒー飲んで脳トレーニング
コーヒーは貧血の特効薬になるか?
コーヒーは冷えるに根拠なし
コーヒーは特保を超えた
飲みすぎは逆効果
コーヒー・卜リビア
その1:最初のチップ
その2:法王から洗礼を受けたコーヒー
その3:ナポレオンとコーヒー
その4:日本初の喫茶店
第2章 どんなコーヒーをどのように飲むといいのか?
アラビ力種と口ブスタ種
浅煎り・深煎りで変わる成分
煎りの深さの違う豆で「成分ブレンド」
がんを予防するコーヒーは
糖尿病を予防するコーヒーは
アルツハイマー病を予防するには
悪玉成分を除く技術
カフェイン入りかデカフェタイプか?
がんを予防するコーヒーは
コーヒーの成分を生かすために覚えておくといいこと
その1:温度と蒸らし時間
その2:コーヒーの種類と作用の違い
〈インスタントコーヒー〉
〈缶コーヒー〉
その3:砂糖とミルク
その4:ダイエットなら食前に
その5:豆の挽き方
その6:コーヒー豆の保存と有効成分
その7:便利な滝れ方・飲み方
コーヒーをよい意味で「癖」にする
1日何杯まで飲んでいいか?
第3章 食と長寿と病気予防
必須栄養素とコーヒーの相乗効果
重要なのは約50種の必須栄養素
なぜ必須栄養素をとらねばならないのか
ポリフ工ノールは混ぜると効く
カロリー制限より必須栄養素
「肉より魚」ではなく「5品より10品」
味と色は栄養選びのめやす
栄養素を助けるコーヒー成分
カルシウムを減らさないコーヒーの飲み方
コーヒーは肝臓の寿命を延ばすか?
コーヒーは尿酸値のバランスをとるか?
コーヒーは「オートファジー」を助けるか?
コーヒーで腸内細菌が元気に
コーヒーは本当に体にいい
コーヒー活用アドバイス
◇35歳、スーパーマーケット店長の減量計画
◇35歳、霞が関キャリアの生活改善
病気の初期症状を見逃すな
ほか
岡 希太郎 (著)
新書判:160ページ(H)17.6cm x (W)11.4cm
出版社:集英社
岡希太郎[おか きたろう]
1941年東京都出身。東京薬科大学名誉教授、金沢大学コーヒー学講座講師。東京薬科大学卒業、薬学博士(東京大学)。スタンフォード大学医学部留学。薬化学と臨床薬理学を専攻。加盟学会:日本薬学会、米国化学会、日本臨床薬理学会、日本コーヒー文化学会他。著書に「臨床薬理学J(朝倉書庖)、「なるほどくすりの原料としくみ」(素朴社)、「コーヒーの処方箋」「珈琲一杯の薬理学」「医食同源のすすめ死ぬまで元気でいたいなら」(以上医薬経済社)等
 お客様の声
お客様の声
商品情報
| 通常価格 | 990円(税込) |
|---|---|
| 在庫 | △ |
| 商品コード | 87587 |

 今月のセール品
今月のセール品 コーヒー
コーヒー 定番銘柄コーヒー
定番銘柄コーヒー ブレンドコーヒー
ブレンドコーヒー アイスコーヒー
アイスコーヒー カフェインレスコーヒー
カフェインレスコーヒー 生豆限定お買得セール
生豆限定お買得セール [送料込]コーヒーメール便
[送料込]コーヒーメール便 世界のコーヒー飲み比べセット
世界のコーヒー飲み比べセット ドリップバッグコーヒー
ドリップバッグコーヒー 1杯から試せるドリップバッグコーヒー
1杯から試せるドリップバッグコーヒー ブリューイングバッグコーヒー
ブリューイングバッグコーヒー ダンク式コーヒーバッグ
ダンク式コーヒーバッグ 水出しコーヒーバッグ
水出しコーヒーバッグ フレーバーコーヒー
フレーバーコーヒー 世界のブランドコーヒー
世界のブランドコーヒー エスプレッソカフェポッド(44mm)
エスプレッソカフェポッド(44mm) カプセルコーヒー
カプセルコーヒー 互換カプセルコーヒー
互換カプセルコーヒー インスタントコーヒー
インスタントコーヒー リキッドコーヒー
リキッドコーヒー スペシャルティコーヒー
スペシャルティコーヒー カップオブエクセレンス
カップオブエクセレンス 限定品コーヒー
限定品コーヒー 焙煎器 (生豆を煎る)
焙煎器 (生豆を煎る) ミル (豆を挽く)
ミル (豆を挽く) ハンドドリップ
ハンドドリップ コーヒーメーカー
コーヒーメーカー コーヒーサイフォン
コーヒーサイフォン コーヒープレス
コーヒープレス エスプレッソメーカー
エスプレッソメーカー パーコレーター
パーコレーター 水出しコーヒー器具
水出しコーヒー器具 アイスコーヒー器具
アイスコーヒー器具 珍しい抽出器具
珍しい抽出器具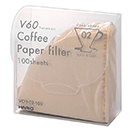 ペーパー&フィルター
ペーパー&フィルター コーヒーサーバー
コーヒーサーバー コーヒーケトル&ポット
コーヒーケトル&ポット コーヒーウォーマー
コーヒーウォーマー キャニスター&真空グッズ
キャニスター&真空グッズ コーヒーメジャースプーン
コーヒーメジャースプーン 麻袋・樽
麻袋・樽 カップ
カップ コーヒースプーン
コーヒースプーン 使い捨てカップ&スプーン
使い捨てカップ&スプーン エスプレッソ用品
エスプレッソ用品 お手入れ用品
お手入れ用品 調理器具&キッチングッズ
調理器具&キッチングッズ マスターのおすすめ商品
マスターのおすすめ商品 便利&面白グッズ
便利&面白グッズ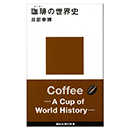 書籍・ビデオ・CD
書籍・ビデオ・CD 紅茶
紅茶 紅茶
紅茶 フレーバーティー
フレーバーティー フルーツティー
フルーツティー ハーブティー
ハーブティー 中国茶
中国茶 日本茶
日本茶 茶葉飲み比べメール便
茶葉飲み比べメール便 その他のティー
その他のティー ティーバッグ
ティーバッグ 水出し茶
水出し茶 インスタントティー
インスタントティー リキッドティー
リキッドティー 紅茶器具&関連用品
紅茶器具&関連用品 お酒
お酒 ココア
ココア 豆乳
豆乳 ジュース
ジュース ミネラルウォーター
ミネラルウォーター その他のドリンク
その他のドリンク 砂糖・ミルク・食品類
砂糖・ミルク・食品類 砂糖&甘味料
砂糖&甘味料 クリーム&ミルク
クリーム&ミルク フレーバー&香料
フレーバー&香料 レトルト食品
レトルト食品 調味料&オイル
調味料&オイル その他の食品
その他の食品 チョコレート
チョコレート キャンディー
キャンディー スナック (焼き菓子)
スナック (焼き菓子) ケーキ・パン類
ケーキ・パン類 デザート
デザート ドライフルーツ
ドライフルーツ その他のお菓子
その他のお菓子 自家焙煎コーヒーギフト
自家焙煎コーヒーギフト アイスコーヒーギフト
アイスコーヒーギフト ドリップバッグコーヒーギフト
ドリップバッグコーヒーギフト ダンク式コーヒーギフト
ダンク式コーヒーギフト インスタントコーヒーギフト
インスタントコーヒーギフト リキッドコーヒーギフト
リキッドコーヒーギフト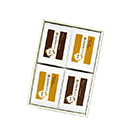 スイーツギフト
スイーツギフト 紅茶ギフト
紅茶ギフト その他ギフト(ギフト箱)
その他ギフト(ギフト箱)
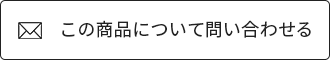
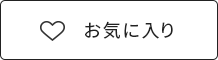

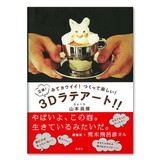









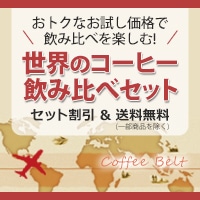

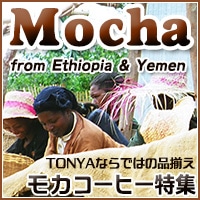


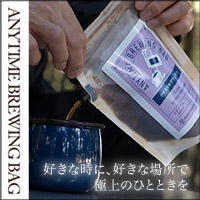





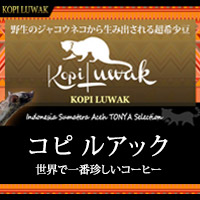
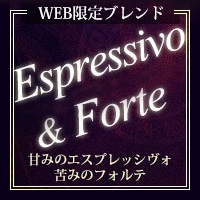




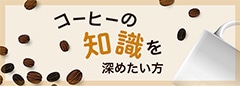
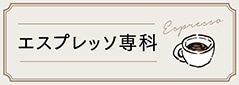
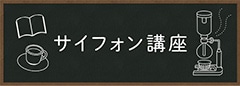

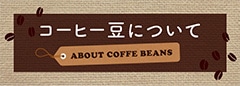






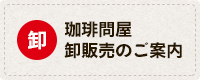
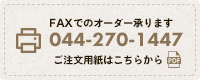



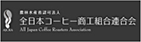


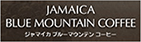

ボケたくなければ、
毎日コーヒーを飲みなさい。
岡 希太郎 (著)
コーヒーに含まれるカフェインとポリフェノールは日本茶よりも多く、その相乗効果がビジネスマンの健康を守る。コーヒーが生活習慣病予防に大いに役立つ飲み物であることをわかりやすく解説。